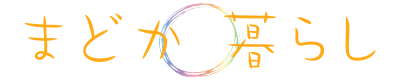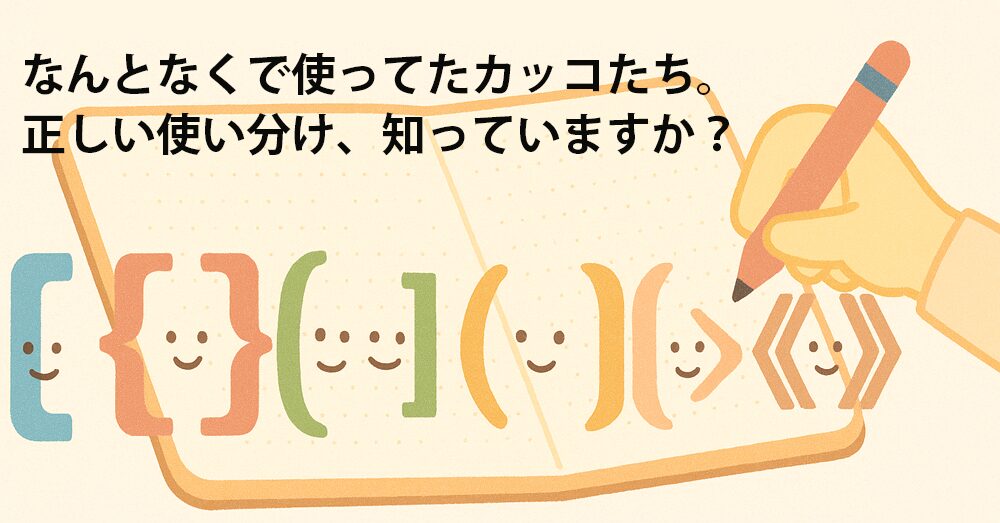「」や『』、()、【】──日本語にはたくさんの「カッコ」がありますよね。
なんとなく使い分けているけれど、実はそれぞれにちゃんとした意味や役割がありました。
今回は、私自身の思い込みや誤解を振り返りながら、括弧の種類と使い分けについて整理してみたいと思います。
私自身、ずっと「」と『』を見た目のバランスだけで使い分けてきました。
たとえば、文章の中にカッコが重なるとき、
『△△△「▲▲▲」△△△』
のような形になる方が、見た目的にしっくりくると感じていたんです。
いわば、【大きいカッコの中に小さいカッコを入れる】という直感的な感覚で、意味やルールはあまり考えていませんでした。
でも最近、引用の表記を調べる機会があって、
「▲▲▲『△△△』▲▲▲」
のように、『』が内側にくることもあるのを知り、目からウロコでした。
そこから、いかに自分が見た目だけで判断していたか、痛感したんです。
カッコの種類と主な使い方
ここで、よく使う括弧の種類と主な用途をざっと整理しておきます。
| カッコ | 名称 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 「 」 | 鉤括弧(かぎかっこ) | 会話、主引用、強調など |
| 『 』 | 二重鉤括弧(にじゅうかぎかっこ) | 書名、引用中の引用など |
| ( ) | 丸括弧 | 補足、注釈など |
| [ ] | 角括弧 | 学術的注釈、引用の補足、校正など |
| 【 】 | 隅付き括弧 | 見出し、ラベル的な使い方 |
| 〈 〉 / 《 》 | 山括弧 / 二重山括弧 | 書名や作品名など(縦書きでよく使われる) |
| 〔 〕 | 波括弧 | 数学や規則文書などで補足的に使う |
| { } | 中括弧 | プログラムや論理構造など、数式系でよく登場 |
| “ ” / ‘ ’ | ダブルクォーテーション / シングルクォーテーション | 主に英語用(日本語には基本的に使わない) |
引用での使い分け:内と外
引用が入れ子になる場合、一般的には
「主な引用の文章『その中の引用』」
のように、**外側に「」、内側に『』**を使います。
逆に、書籍名や新聞名が先にあって、
『日本経済新聞「生成AIの未来」』
のようなケースでは、『』が外側にきて、「」が内側になります。
つまり、文脈によって入れ子の構造は入れ替わるのです。
私の誤解
私自身は、文の中にカッコが重なると、なんとなく
『大きなカッコ「小さなカッコ」大きなカッコ』
のように、【見た目のサイズ感】で組み合わせていたところがありました。
でも、それはあくまで視覚的な誤解であって、実際の使い方は意味や構造に基づいて変わるもの。
たとえば、会話の中で誰かの発言を引用する場合は、
「先日の『生成AIの未来』という記事、読んだ?」
のように「」が外で、『』が内、という構造になります。
まとめ
カッコの使い分けは、ルールがあるようで、文脈によって柔軟に変わる面もあります。
大切なのは、「なんとなく見た目」ではなく、
- 何を囲っているのか(発言?引用?作品名?)
- どの情報が主で、どれが補足なのか
といった意味の構造に目を向けることだと学びました。
以上、日本語でよく使うさまざまなカッコの種類と、それぞれの意味・使い分けについてまとめてみました。
自分自身の備忘録として、そして「知らなかった!」という誰かの参考になればうれしいです。